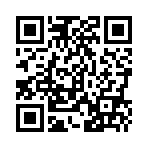2024年07月14日
沖縄関連観覧まとめ
沖縄はいつだって平和や戦争を考えざるを得ない状況にあるわけで……必要なことではあるけれども、普段の生活の中でちくりとささる棘のように意識せざるを得ないと言うのはやはり幸せとは言えないよなと思ったりです。慰霊の日が6月にあることからどうしても6月に沖縄戦関係の催しが多くなります。ざっくりと振り返ってみます。
ACO沖縄の舞台「洞窟 ガマ」
舞台「洞窟(ガマ)」は、タイトルの通り、ガマ・・・洞窟の中が物語の舞台で、脚本は沖縄出身の嶋津与志さん。初演は1980年、東京のパモス青芸館。現在までに60回ほど公演を行っています。
脚本の嶋津与志さんは多くの方の体験を聞く中で、光の当たらない、埋もれた体験に光を当てなくてはと思ったそうです。沖縄戦では、沖縄県民の4人に1人が亡くなったとされています。亡くなった1人ではなく、生き残った3人がどのようにして命を繋ぐことになったのかを表現したのが舞台「洞窟」です。日本軍の兵隊と、沖縄の住民は暗いガマで同居せざるを得ない状況。極限の状態での葛藤が描かれています。
私は初日を観覧しました。いつもの舞台配置ではなく、スペースの真ん中にドーンとガマのセットがあり、それを取り囲むように客席が配置されていました。最初はいつもと違うなという程度でしたが、舞台が進むにしたがい、私たち観客もまたガマで息を潜めていた人々として舞台に参加しているのだと気づきます。今回は特に演出という仕事が、どのようにしたら観客により届くのかを考える仕事なのだと実感しました。
戦争という極限状態……特に沖縄戦は連合国軍との圧倒的な戦力の差がある中での負け戦でした。日本軍が南部に撤退し、牛島司令官が自決した後はさらに情報が得られず、より混沌としたことでしょう。追い詰められると人間はどうなるのか。人として誠実でありたいと思いながらもできなくなってゆく様が描かれていました。1980年の初演から44年経過しても色褪せることのないメッセージに、作者の強い思いに感動すると共に、沖縄の置かれている状況が何も変わっていないということにやるせない気持ちになりました。
一つ残念なのは、日本兵役の俳優さんが恫喝するシーンで台詞がよく聞き取れなかったところ。舞台上は台詞という約束で進んでいくので、聞き取りにくい発話であっても進んでいきます。しかし、観客は「今、なんて言ったの? 次の人がこういう行動だから多分こういう意味のことを言ったのか」と理解に時間がかかってしまい、少々疲れました。私が携わっているのは音声表現ですが、聞き取ってもらえる音声というのが前提にあるので気になりました。
舞台を見た後に、たまたま「便衣兵」という言葉を知りました。便衣兵とは住民に偽装して戦闘を行う軍人という意味だそうです。舞台「洞窟(ガマ)」の中にも、沖縄の着物を着た軍人が出てきます。どの戦争でもあることなのかもしれないですが、沖縄戦がいかに住民を巻き込んだ戦争だったかが分かりました。
舞台「ライカムで待っとく」
舞台「ライカムで待っとく」は、沖縄在住の劇作家・兼島拓也さんが脚本。沖縄に出自を持つ田中麻衣子さんが演出を手がけ、沖縄の本土復帰50年の年にKAAT(カート)神奈川芸術劇場のプロデュースで上演されました。神奈川、京都、福岡をめぐり、今年、ようやく沖縄で上演されることになりました。
舞台「ライカムで待っとく」の物語は、雑誌記者の浅野が60年前の沖縄で起きた米兵殺傷事件について調べることになったところから始まります。調べるうちに、実はその容疑者が自分の妻の祖父・佐久本だったことを知ります。浅野は次第に沖縄の過去と現在が渾然となった不可解な中で、飲み込まれてゆきます。
この舞台に先立ち、記者を案内するタクシー運転手役の佐久本宝さんに取材する機会がありました。その中で「今と昔を行ったり来たりするので、何が正解かわからない」とお話していました。確かに記者が取材する過去、そして記者が身を置いている現在とが交差する内容で、今自分はどこにいるのかと少々混乱しました。しかし、その混乱こそが舞台のテーマのような気がします。
舞台を見たのは6月22日のことですが、7月に入って去年12月、そして今年の5月に米兵による性的暴行事件があったと分かりました。政府は事件が起こったことを把握していましたが、沖縄県に知らせませんでした。沖縄県や県民が事件を知ったのは県議会選挙が終わってから。新聞社の取材によってでした。新聞社が取材しなければ、もしかしたらずっと知らずにいたかもしれません。そして7月10日、米軍横田基地でPFAS漏れ事故を日米両政府が非公表と合意した件が報道されました。周辺住民の健康に影響があるかもしれないことを黙っているとはどういうことなのでしょう。今、私が暮らしているのは日本なのでしょうか? まだ米軍統治下にあるのでしょうか? 混乱する出来事が現在進行形で起こっています。
舞台「ライカムで待っとく」は、沖縄の本当にあった事件を元に制作された舞台ですが、沖縄以外の地域でも同じことが起こっている、起ころうとしているのだと思います。先に記した舞台「洞窟」のように、長く、またあちらこちらで上演される舞台になって欲しいと思いました。今、思い返してもわからない部分はあり、混乱してはいますが。それはそれでいいのだと思います。
舞台「10カウント ある老ボクサーの夢」
こちらは先日舞台評の件で触れたので、詳細は省きますが、いつまでも沖縄は理不尽な状況にあるなあと思い、やるせなさが募りました。同時にこれまで本土を拠点に活動してきた津嘉山正種さんが、沖縄の魂シリーズと題して取り組んできた姿勢に考えることがありました。
津嘉山さんがどのような気持ちであるかは直接お話を伺ったことがないのではっきりと分かりませんが、年を重ね、ふと自分の足元を見た時に沖縄があった。その沖縄はまだ理不尽の中にいた。何かしなくてはという気持ちになったのではないでしょうか。
私は2015年から小説を書くようになりました。それは小説家になりたいわけではなく、父母の戦争体験をどうにか伝えられないかというところからの行動でした。実は大学卒業後、沖縄に戻ってくるまで沖縄に関心がありませんでした。いつまでもどこか泥臭くやぼったい沖縄から早く出たくて仕方ありませんでした。結局、沖縄で仕事の縁があり、戻ってきて現在に至ります。沖縄で放送の仕事に関わるということは、沖縄のことを知らないとできません。最初は何も知らず……今でも十分ではありませんが、泣きながら勉強し、また放送の現場に向かうという毎日でした。そんな中から「もっと学ばなくては。両親が元気なうちに届けないといけないことがある。沖縄が前進するための何かを」と気付き、書いています。津嘉山さんも同じような気持ちなのではないかなと、勝手に思っています。
映画「骨を掘る男」
こちらは6月22日に桜坂劇場で公開となったドキュメンタリー映画です。「ガマフヤー(洞窟掘り)」と呼ばれている具志堅隆松さんを追いかけた映画です。
もうどれくらい前のことか……具志堅さんにお話を伺ったことがあります。その時にもなぜ自ら遺骨収集をしているのか、それもずっとずっと無償で続けているのかよく理解できませんでした。簡単なことではないですから。映画では具志堅さんを追いかけ、また監督の家族の沖縄戦を追い、それが現在と交差します。
誰のものかわからない遺骨ですが、その遺骨になってしまった人を待っている人がまだ多くいるのだと思うと切なくなります。私の母は沖縄戦末期、南部に逃げ、そこで父母と妹を失いました。母は当時4、5歳だったので、どこを歩いて、どこで家族が死に、遺体がどこにあるか覚えていません。だから、毎年、摩文仁の戦没者墓苑に手を合わせにいきます。誰かが骨を拾ってくれたのならここにあるだろうと。
この映画でも触れていますが、まだ沖縄戦の戦没者の骨があるであろう南部地域の土が、辺野古の埋め立て工事に使われています。感情論を振りかざすわけではありませんが、反戦平和を訴える島に基地が増えてゆく。その基地を作る材料に、島の土……沖縄戦で死んだ人の血が染み込み、骨が残る島の土を使う。悪い冗談のようなことが現在進行形で起きています。また、南西諸島防衛の名目でどんどん自衛隊の基地が出来ています。沖縄の基地負担軽減はどこへという状態で、日毎にきな臭くなっています。
具志堅さんのように取り組むことはできずとも、無関心からの脱却はすべきではないでしょうか。今、私があるということ。物言わぬ骨となった人たちが、私の後ろに連なっていると思えば、無関心ではいられないと思うのです。

ACO沖縄の舞台「洞窟 ガマ」
舞台「洞窟(ガマ)」は、タイトルの通り、ガマ・・・洞窟の中が物語の舞台で、脚本は沖縄出身の嶋津与志さん。初演は1980年、東京のパモス青芸館。現在までに60回ほど公演を行っています。
脚本の嶋津与志さんは多くの方の体験を聞く中で、光の当たらない、埋もれた体験に光を当てなくてはと思ったそうです。沖縄戦では、沖縄県民の4人に1人が亡くなったとされています。亡くなった1人ではなく、生き残った3人がどのようにして命を繋ぐことになったのかを表現したのが舞台「洞窟」です。日本軍の兵隊と、沖縄の住民は暗いガマで同居せざるを得ない状況。極限の状態での葛藤が描かれています。
私は初日を観覧しました。いつもの舞台配置ではなく、スペースの真ん中にドーンとガマのセットがあり、それを取り囲むように客席が配置されていました。最初はいつもと違うなという程度でしたが、舞台が進むにしたがい、私たち観客もまたガマで息を潜めていた人々として舞台に参加しているのだと気づきます。今回は特に演出という仕事が、どのようにしたら観客により届くのかを考える仕事なのだと実感しました。
戦争という極限状態……特に沖縄戦は連合国軍との圧倒的な戦力の差がある中での負け戦でした。日本軍が南部に撤退し、牛島司令官が自決した後はさらに情報が得られず、より混沌としたことでしょう。追い詰められると人間はどうなるのか。人として誠実でありたいと思いながらもできなくなってゆく様が描かれていました。1980年の初演から44年経過しても色褪せることのないメッセージに、作者の強い思いに感動すると共に、沖縄の置かれている状況が何も変わっていないということにやるせない気持ちになりました。
一つ残念なのは、日本兵役の俳優さんが恫喝するシーンで台詞がよく聞き取れなかったところ。舞台上は台詞という約束で進んでいくので、聞き取りにくい発話であっても進んでいきます。しかし、観客は「今、なんて言ったの? 次の人がこういう行動だから多分こういう意味のことを言ったのか」と理解に時間がかかってしまい、少々疲れました。私が携わっているのは音声表現ですが、聞き取ってもらえる音声というのが前提にあるので気になりました。
舞台を見た後に、たまたま「便衣兵」という言葉を知りました。便衣兵とは住民に偽装して戦闘を行う軍人という意味だそうです。舞台「洞窟(ガマ)」の中にも、沖縄の着物を着た軍人が出てきます。どの戦争でもあることなのかもしれないですが、沖縄戦がいかに住民を巻き込んだ戦争だったかが分かりました。
舞台「ライカムで待っとく」
舞台「ライカムで待っとく」は、沖縄在住の劇作家・兼島拓也さんが脚本。沖縄に出自を持つ田中麻衣子さんが演出を手がけ、沖縄の本土復帰50年の年にKAAT(カート)神奈川芸術劇場のプロデュースで上演されました。神奈川、京都、福岡をめぐり、今年、ようやく沖縄で上演されることになりました。
舞台「ライカムで待っとく」の物語は、雑誌記者の浅野が60年前の沖縄で起きた米兵殺傷事件について調べることになったところから始まります。調べるうちに、実はその容疑者が自分の妻の祖父・佐久本だったことを知ります。浅野は次第に沖縄の過去と現在が渾然となった不可解な中で、飲み込まれてゆきます。
この舞台に先立ち、記者を案内するタクシー運転手役の佐久本宝さんに取材する機会がありました。その中で「今と昔を行ったり来たりするので、何が正解かわからない」とお話していました。確かに記者が取材する過去、そして記者が身を置いている現在とが交差する内容で、今自分はどこにいるのかと少々混乱しました。しかし、その混乱こそが舞台のテーマのような気がします。
舞台を見たのは6月22日のことですが、7月に入って去年12月、そして今年の5月に米兵による性的暴行事件があったと分かりました。政府は事件が起こったことを把握していましたが、沖縄県に知らせませんでした。沖縄県や県民が事件を知ったのは県議会選挙が終わってから。新聞社の取材によってでした。新聞社が取材しなければ、もしかしたらずっと知らずにいたかもしれません。そして7月10日、米軍横田基地でPFAS漏れ事故を日米両政府が非公表と合意した件が報道されました。周辺住民の健康に影響があるかもしれないことを黙っているとはどういうことなのでしょう。今、私が暮らしているのは日本なのでしょうか? まだ米軍統治下にあるのでしょうか? 混乱する出来事が現在進行形で起こっています。
舞台「ライカムで待っとく」は、沖縄の本当にあった事件を元に制作された舞台ですが、沖縄以外の地域でも同じことが起こっている、起ころうとしているのだと思います。先に記した舞台「洞窟」のように、長く、またあちらこちらで上演される舞台になって欲しいと思いました。今、思い返してもわからない部分はあり、混乱してはいますが。それはそれでいいのだと思います。
舞台「10カウント ある老ボクサーの夢」
こちらは先日舞台評の件で触れたので、詳細は省きますが、いつまでも沖縄は理不尽な状況にあるなあと思い、やるせなさが募りました。同時にこれまで本土を拠点に活動してきた津嘉山正種さんが、沖縄の魂シリーズと題して取り組んできた姿勢に考えることがありました。
津嘉山さんがどのような気持ちであるかは直接お話を伺ったことがないのではっきりと分かりませんが、年を重ね、ふと自分の足元を見た時に沖縄があった。その沖縄はまだ理不尽の中にいた。何かしなくてはという気持ちになったのではないでしょうか。
私は2015年から小説を書くようになりました。それは小説家になりたいわけではなく、父母の戦争体験をどうにか伝えられないかというところからの行動でした。実は大学卒業後、沖縄に戻ってくるまで沖縄に関心がありませんでした。いつまでもどこか泥臭くやぼったい沖縄から早く出たくて仕方ありませんでした。結局、沖縄で仕事の縁があり、戻ってきて現在に至ります。沖縄で放送の仕事に関わるということは、沖縄のことを知らないとできません。最初は何も知らず……今でも十分ではありませんが、泣きながら勉強し、また放送の現場に向かうという毎日でした。そんな中から「もっと学ばなくては。両親が元気なうちに届けないといけないことがある。沖縄が前進するための何かを」と気付き、書いています。津嘉山さんも同じような気持ちなのではないかなと、勝手に思っています。
映画「骨を掘る男」
こちらは6月22日に桜坂劇場で公開となったドキュメンタリー映画です。「ガマフヤー(洞窟掘り)」と呼ばれている具志堅隆松さんを追いかけた映画です。
もうどれくらい前のことか……具志堅さんにお話を伺ったことがあります。その時にもなぜ自ら遺骨収集をしているのか、それもずっとずっと無償で続けているのかよく理解できませんでした。簡単なことではないですから。映画では具志堅さんを追いかけ、また監督の家族の沖縄戦を追い、それが現在と交差します。
誰のものかわからない遺骨ですが、その遺骨になってしまった人を待っている人がまだ多くいるのだと思うと切なくなります。私の母は沖縄戦末期、南部に逃げ、そこで父母と妹を失いました。母は当時4、5歳だったので、どこを歩いて、どこで家族が死に、遺体がどこにあるか覚えていません。だから、毎年、摩文仁の戦没者墓苑に手を合わせにいきます。誰かが骨を拾ってくれたのならここにあるだろうと。
この映画でも触れていますが、まだ沖縄戦の戦没者の骨があるであろう南部地域の土が、辺野古の埋め立て工事に使われています。感情論を振りかざすわけではありませんが、反戦平和を訴える島に基地が増えてゆく。その基地を作る材料に、島の土……沖縄戦で死んだ人の血が染み込み、骨が残る島の土を使う。悪い冗談のようなことが現在進行形で起きています。また、南西諸島防衛の名目でどんどん自衛隊の基地が出来ています。沖縄の基地負担軽減はどこへという状態で、日毎にきな臭くなっています。
具志堅さんのように取り組むことはできずとも、無関心からの脱却はすべきではないでしょうか。今、私があるということ。物言わぬ骨となった人たちが、私の後ろに連なっていると思えば、無関心ではいられないと思うのです。

Posted by ぱな87 at 23:07│Comments(0)
│書き描き下記?